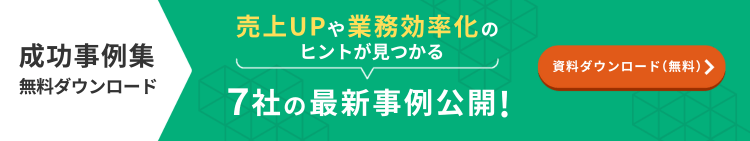売掛債権とは?種類や管理方法、未回収リスクの回避ポイントを解説

企業間取引において、「売掛債権」という言葉は頻繁に登場します。しかし、具体的にどのような仕組みで発生し、どのように管理すべきなのかを理解している方は少ないかもしれません。また、売掛債権は未回収リスクと密接に関連しており、適切な管理を怠ると企業の経営に大きな影響を与える可能性があります。本記事では、売掛債権の基本的な仕組みや種類、管理方法を解説するとともに、未回収リスクを回避するポイントについても詳しくお伝えします。
目次
売掛債権とは?
売掛債権とは、企業が商品やサービスを提供した際に発生する「まだ支払われていない代金の請求権」を指します。例えば、企業Aが企業Bに商品を販売し、支払いを後日行う条件で契約した場合、企業Aには売掛債権が発生します。これは、言い換えれば「取引先から将来受け取るお金を得る権利」を表しています。会計上、売掛債権は取引先からの支払いが確実である限り、将来的に現金として企業に利益をもたらす資産であるため「流動資産」に分類されます。
また売掛債権には、法律上の「消滅時効」が適用されます。債権者が支払いを求める権利を一定の期間内に行使しなかった場合に、法的にその権利が消滅することを意味します。時効期間は、通常5年です(民法第167条)。つまり、売掛金の請求権は、取引が成立してから5年を経過することで消滅します。ただし、時効期間の起算点は、契約内容や状況により異なる場合があるため、注意が必要です。売掛金の時効が成立すると、債権者は法的に回収を求めることができなくなります。
関連記事:売掛金の消滅時効とは?時効の成立を防ぐ方法や中断・更新措置について解説
売掛債権の種類と特徴
売掛債権には、「売掛金」「受取手形」「電子記録債権」の3つの代表的な種類があります。それぞれの仕組みや特徴を理解し、適切に管理することが、企業のリスク軽減や資金繰りの安定につながります。
売掛金
売掛金とは、企業が商品やサービスを提供した際、取引先から後日支払われる予定の代金を指します。これは、販売時点では現金を受け取らず、後払いの契約にもとづく売上金の一部として計上されます。売掛金は企業間取引でよく見られますが、信用取引の一環として発生するため、取引先との信頼関係が重要です。
売掛手形
受取手形も売掛金と同じく後払いで取引した際に受け取るべき代金ですが、取引先から手形(支払期日が記載された証書)を受け取ることで発生するのが特徴です。手形には具体的な支払期日が記載されており、その期日に指定された銀行で現金化することが可能です。受取手形は、融資の担保として利用できる場合があります。
取引先が手形の支払いを行わない場合(不渡り)、債権の回収が困難になるリスクがあり点は注意が必要です。
電子記録債権
電子記録債権とは、電子的に記録・管理される売掛債権の一種で、2008年に施行された「電子記録債権法」にもとづいて活用されています。具体的には、取引内容や支払期日などをデータベース上で管理する仕組みです。紙の手形や請求書を必要とせず、金融機関によって自動化に現金化されるため、管理が効率化するのも特徴です。
売掛債権の管理方法
売掛債権の管理は、企業のキャッシュフローを安定させ、未回収リスクを軽減するために欠かせません。このセクションでは、基本的な管理の考え方から具体的な方法を解説します。
売掛債権管理の基本
売掛債権管理とは、取引先への請求から入金までの流れを適切に把握し、未回収の発生を防ぐプロセスを指します。管理を怠ると、以下のようなリスクが発生します。
- 資金繰りの悪化
- 不良債権の発生
- 取引先との信頼関係の損失
売掛債権の管理プロセス
上記のリスクを回避するためには、以下の基本的なプロセスを守る必要があります。
- 与信取引の限度額を決める
- 取引先の支払い能力(信用)を調べる。
- 与信取引の限度額を設定する。
- 請求書発行と確認
- 正確で漏れのない請求書を発行する。
- 請求内容(取引内容や金額)が取引先と合意した内容と一致しているかを確認する。
- 入金確認と未回収状況の把握
- 取引先ごとに入金状況を記録し、未回収の状況をリアルタイムで把握する。
- 入金予定日を過ぎた場合、速やかに取引先に確認を行う。
- 継続的な見直し
- 定期的に取引先の信用状況や与信枠を見直し、不安要素があれば取引条件を再検討する。
売掛債権に伴う未回収リスクとその回避策
売掛債権において最も懸念されるのが、取引先から代金を回収できない「未回収リスク」です。未回収リスクを完全にゼロにすることは困難ですが、適切な対策を講じることで、そのリスクを大幅に軽減することが可能です。以下の3つの対策を重点的に実施しましょう。
与信管理の徹底
取引先の信用状況を事前に調査し、適切な与信枠を設定することは、未回収リスクを防ぐための基本です。取引先の決算書や支払い履歴、外部の信用調査機関の情報を活用して、取引先の支払い能力を正確に把握しましょう。また与信枠は取引開始時だけでなく、取引先の業績や経済状況の変化に応じて定期的に見直す必要があります。与信管理を徹底することで、不良債権の発生を未然に防ぎ、安定した取引関係を築けます。
契約書・請求書の明確化
取引条件や支払期日を明確にし、文書化しておくことで、未回収リスクを減らせます。商品やサービスの内容、支払期日、延滞時の対応などを明記した契約書を締結することで、双方の認識を統一することができます。請求書には、取引内容、金額、支払期日、振込先などを正確に記載します。また、請求書のフォーマットを統一し、取引先が確認しやすい形で提出することが重要です。契約書や請求書を適切に整備することで、支払いトラブルを回避しやすくなります。
保険や代行サービスの活用
万が一未回収が発生した場合でも、損失を最小限に抑えるために、保険や外部サービスを活用する方法があります。例えば、売掛債権の保証サービスでは、取引先が倒産した場合などに未回収額を全額保証してくれるので予想外の損失を防げます。
売掛債権管理を効率化し、未回収を防ぐなら「Paid」
企業間決済代行の「Paid(ペイド)」は、掛け取引で発生する請求業務をすべて代行し、万が一未回収になった場合も代金を100%保証します。Paidを利用することによって、売掛債権の管理を効率化することができ、また未回収の心配をする必要がなくなります。
Paidの導入により未回収がなくなり、キャッシュフローを改善できた事例を紹介します。
| 導入企業 | 株式会社coco |
|---|---|
| 業種 | 定額・サブスクリプション |
- Paid導入前の課題
もともと自社で銀行振込に対応していましたが、バックオフィス担当も1名しかいない中で、50件ほどの取引先に対して請求書作成ソフトを使って1枚ずつ請求書を発行して送付して、という作業に非常に手間がかかっていました。
また未入金も毎月5~10件発生しており、架電をして請求書を再発行したり、場合によっては現状の入金の状況をメールで連絡したりと、回収業務にもかなりの時間を取られているが課題でした。
- Paid導入後の効果
毎月発生していた回収業務がすべてなくなりましたし、請求書の発行に関しても今までは2日ほどかかっていたのが、初回の取引先の登録とCSVの内容を確認して受注登録するだけでよくなったので、半日以内で終わるようになっています。
スタートアップは「ランウェイ(キャッシュ不足になるまでの残りの期間)」というのを毎月投資家に報告しないといけないのですが、そのランウェイが非常に長くなりました。たとえば月に100万あるだけでランウェイは何ヵ月も変わってくるのですが、代金が100%保証されるだけでこんなに変わるんだなと。そこではじめて今まで回収漏れがかなり多かったということにも気が付きました。
関連記事:請求業務の効率化だけでなく、キャッシュフローが安定したことも大きなメリット~株式会社cocoの事例
まとめ
売掛金と債権の管理は、企業にとって重要な財務活動であり、適切に取り組むことで資金繰りを安定させ、回収リスクを最小限に抑えることができます。売掛金の管理には、契約書をしっかりと作成し、支払期日や遅延損害金を明確にすることが重要です。また、回収方法や未回収リスクへの対策として、信用調査や取引信用保険の活用が有効です。さらに、時効の概念を理解し、売掛金の請求権が時効により消失しないように定期的な請求や債務承認を文書化することで、回収活動をサポートできます。
企業はこれらの知識をもとに、売掛金と債権に関する法的対策を講じることで、健全なキャッシュフローの維持を図り、経営の安定性を高めることが可能です。