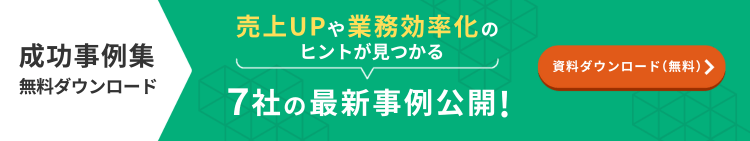収納代行サービスの手数料の相場と仕組みとは?契約前に知っておくべき基礎知識
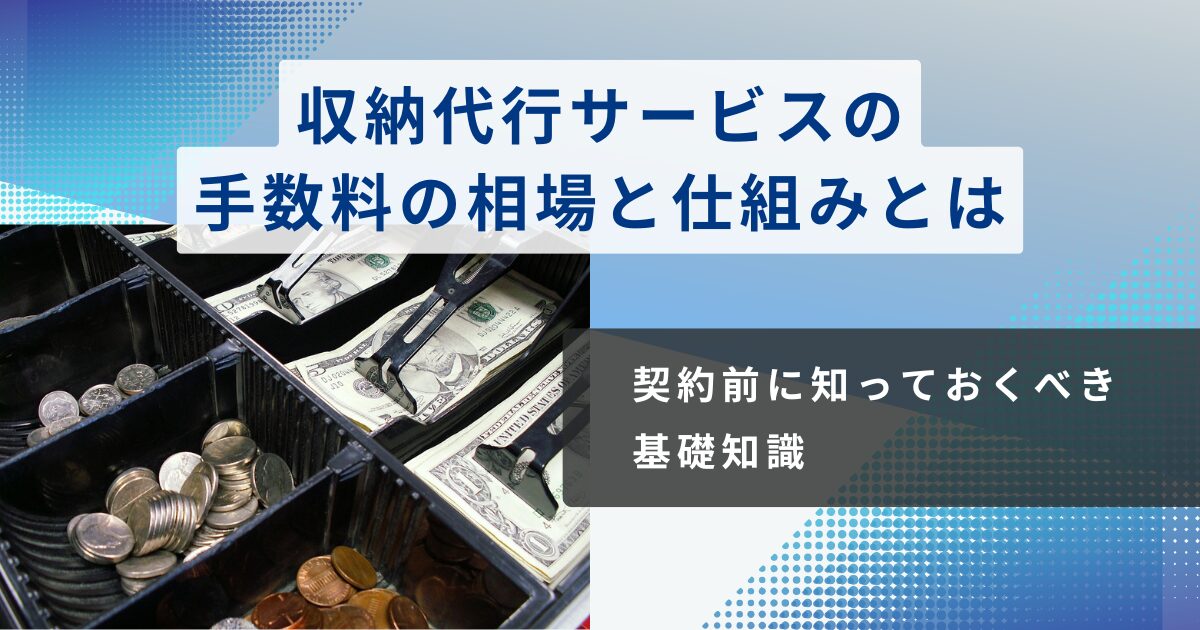
商品の購入代金やサービス料金の支払い手段として、コンビニ払いを導入できる「収納代行サービス」は、多くの企業にとって欠かせないサービスとなっています。しかし導入を検討する際、見逃せないのが手数料の仕組みとそのコスト構造です。
この記事では、収納代行サービスにかかる手数料の仕組みや相場、契約前に注意すべきポイントをわかりやすく解説していきます。
目次
収納代行サービスの手数料とは?基本知識と仕組み
収納代行サービスの手数料とは、どのような費用が発生し、誰が負担するのか――まずは仕組みの全体像を押さえておきましょう。
手数料が発生する仕組みとその内訳
収納代行サービスの手数料は、次のような流れで発生します。
・顧客がコンビニや銀行などの提携店舗で商品代金等を支払う
・支払い情報と代金が、コンビニ店舗 → コンビニ本部 → 収納代行会社 → 事業者へと送金・通知される
・この代行・送金業務に対して、事業者が収納代行会社に手数料を支払う
この手数料の内訳は、一般的に以下の3つに分類されます
・初期費用:サービス導入時にかかる契約・システム連携費用(数万円程度が相場)
・月額費用:システム利用やサポートに対する定額料金(0〜数千円/月)
・収納手数料(決済手数料):1件あたり○円といった従量課金制が基本(例:120〜300円/件)
さらに、バーコード発行や帳票印刷など、オプション機能を利用する場合には追加費用が発生することもあります。
収納代行の手数料は誰が負担するのか?
収納代行サービスにおける手数料の負担者は、基本的に事業者側です。つまり、商品やサービスの提供者(ECサイト運営者や公共料金の請求元など)が、収納代行会社に対して支払います。
顧客は、代金を支払うだけで追加手数料を求められることはほとんどありません。これは、事業者が利便性を高めて顧客の支払いハードルを下げるための施策の一環として、手数料を事業者側で吸収しているケースが多いためです。
ただし、ビジネスモデルや決済手段によって例外も存在します。たとえば、チケット販売サイトなどでは「コンビニ支払手数料」として顧客が100〜300円程度を負担する仕組みもあり、契約内容や業種によって異なります。
収納代行サービスの手数料相場と料金体系
収納代行サービスでは、主に「初期費用」「月額費用」「収納手数料(従量課金)」の3つのコストが発生します。それぞれの相場感を見ていきましょう。
収納代行サービスの手数料の相場は?初期費用・月額費用の目安
・初期費用:0〜5万円前後
契約手続きやシステム設定費用です。一般的には数千円〜5万円程度かかります。しかし、現在は初期費用無料の企業が多い傾向です。
・月額費用:無料〜数万円前後
管理画面の利用やサポートなどにかかる費用です。小規模なら無料〜数千円、中規模以上では1万円前後が相場です。
・収納手数料:1件あたり100〜300円前後
件数が多い場合はボリュームディスカウントが適用されることもあります。
「月額費用が安い=お得」とは限りません。実際の利用件数やサポート体制を含め、総合的に比較することが大切です。
手数料以外に注意すべきコスト・条件
収納代行サービスでは、単価以外にも「最低利用料金」や「回収件数に応じた加算料金」といったコストが発生する場合があります。これらは見落としがちですが、実際のコストに大きく影響する要素です。
最低利用料金
最低利用料金とは、取引件数に関わらず毎月一定額以上が請求される仕組みです。たとえば月額3,000~10,000円程度が設定されていることが多く、利用件数が少ない場合には1件あたりのコストが割高になる可能性があります。少数取引の企業やスタートアップには注意が必要です。
回収件数による加算項目
また、回収件数による加算も重要です。多くのサービスでは、月間◯件までは一定単価、それを超えると追加料金が発生する段階制を採用しています。たとえば、100件までは1件150円、101件目以降は1件200円というような設定です。件数が増える月には、想定以上の出費となるリスクがあります。
解約・契約更新時の手数料・違約金はあるか?
収納代行サービスを導入する際は、解約や更新時の条件も事前に確認しておく必要があります。思わぬ手数料や手続きの煩雑さが、後で負担となることがあるためです。
まず、中途解約に違約金が発生する場合があります。たとえば「最低契約期間1年」などの条件が設定されており、更新月以外の解約で数千円~数万円の費用が発生することも。特に短期間の利用を想定している企業は注意が必要です。
また、契約更新時に手数料がかかる場合もあります。自動更新が多い一方で、プラン変更時などには追加費用が発生する可能性もあります。
領収書や明細の発行コストと管理負担
収納代行サービスを利用する際は、領収書や明細の発行に関わる費用と手間にも注意が必要です。
多くのサービスでは、自動で領収書や明細書を発行できますが、これはオプション扱いとなることがあり、月額費用や件数ごとの追加料金が発生することがあります。特に郵送対応では、印刷や封入、送料などのコストがかさむ点に留意しましょう。
また、データの保存期間が短いサービスでは、一定期間後に明細が削除されるため、自社での保管や出力作業が必要になる場合もあります。
収納代行サービスを手数料で比較する際のポイント
収納代行サービスを選ぶ際、手数料単価の安さだけで判断するのは危険です。たとえ1件あたりのコストが安く見えても、トラブル対応や導入後の運用で手間やコストが増加するケースも少なくありません。
たとえば、導入時のサポート体制が整っていない場合、初期設定やシステム連携で想定以上の時間を要することがあります。また、問い合わせへのレスポンスが遅い業者や、トラブル時の対応が不十分な会社では、回収漏れや顧客対応に支障が出るリスクも。
さらに、導入実績の少ない業者の場合、特定業種へのノウハウが乏しく、運用の最適化が難しいことも考えられます。一方、豊富な実績を持つ企業であれば、業種特化の機能や柔軟な対応が期待できるため、長期的なコストパフォーマンスが高まります。
目的別おすすめ業者3選(コスト重視/サポート重視など)
収納代行サービスを選ぶ際には、単なる料金比較だけでなく、導入目的や業務特性に応じた視点での選定が重要です。ここでは「コスト重視」「サポート重視」「法人(BtoB)向け」という3つの軸で、実在するサービスを紹介します。
【コスト重視】リコーリースの集金代行サービス
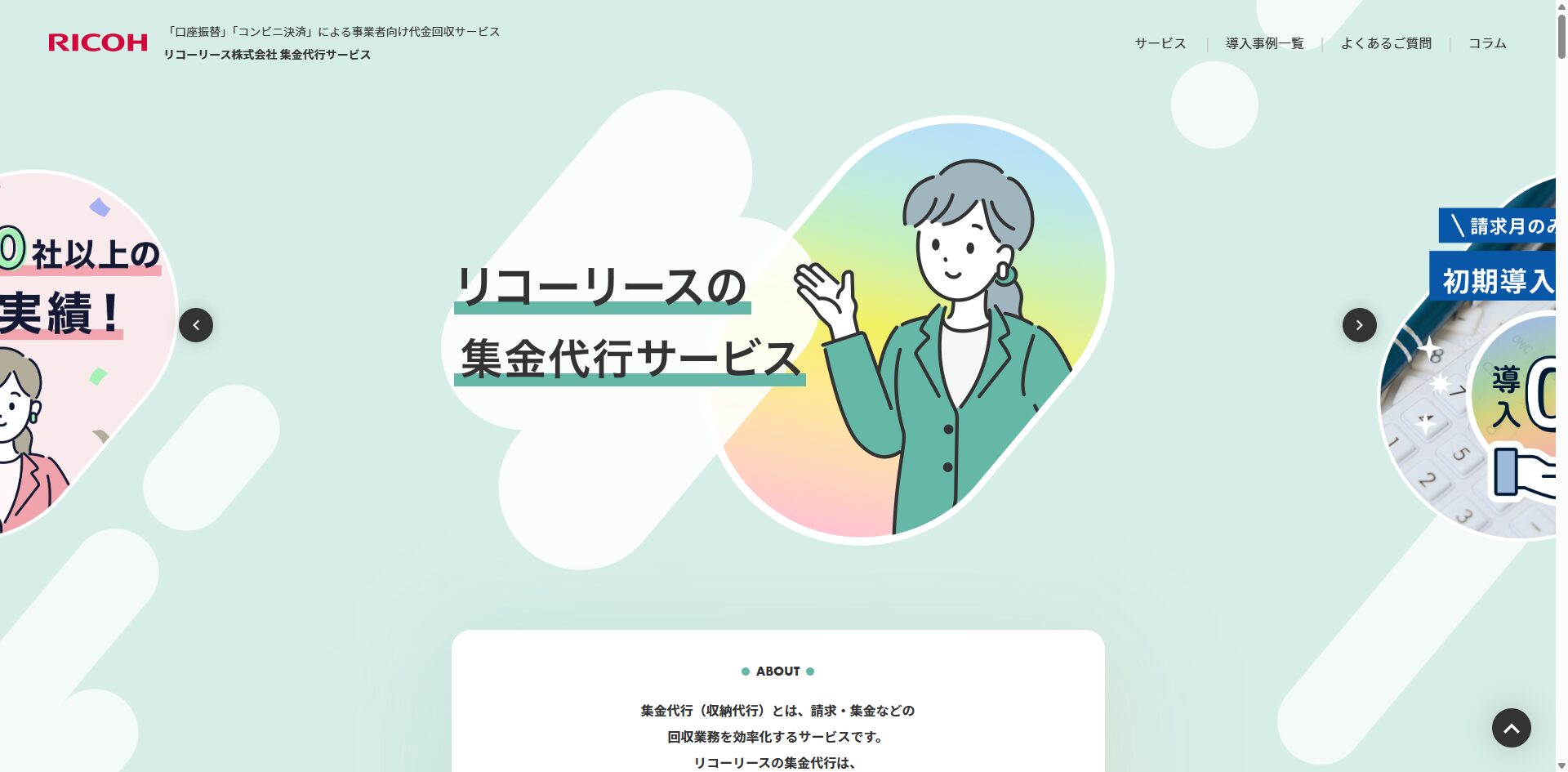
リコーリースが提供する集金代行サービスは、コンビニ払いと口座振替に対応しています。リコーグループとして約40年間安定したサービス提供をしてきた実績があります。
導入費用が一切かからないのが特徴で、サービスを始めたてでまだ請求件数が少ない場合でも、コストの負担を気にせず利用することができます。また導入時のサポートだけでなく、導入後の専用フリーダイヤルも用意されているので安心です。
【サポート重視】アプラス集金代行

https://syukin.aplus.co.jp/service/convenience/
アプラスは、SBI新生銀行グループに属し、40年以上・8,000社以上の導入実績を持つ老舗の収納代行会社です。約68,000店のコンビニに対応しており、オプションでスマホアプリ決済も可能です。スマホアプリ決済では、払込票に記載されたバーコードをアプリで読み込むだけで支払いができるため、より高い回収率が期待できます。 導入にあたっての細やかなサポート・運用支援があることも同社の強みです。
【BtoB・法人向け】決済代行サービス「Paid(ペイド)」

Paid(ペイド)は、BtoB取引に特化した決済代行サービスで、コンビニ払い、口座振替、銀行振込に対応しています。与信審査から請求書発行、入金確認、督促対応までを一括で代行し、さらに未回収時の保証もあるため、集金業務の効率化と未回収リスクの低減を同時に実現できます。督促を電話やメールでしっかりと行うのが特徴で、回収率が高いため、SaaSなど利用継続率を改善したい企業には大きなメリットとなります。導入実績は5,500社以上で、幅広い業種・業界に導入されています。
申し込みから開始までのステップと所要期間
収納代行サービスの導入は、単に申し込むだけで完了するものではありません。スムーズに開始するためには、各ステップの内容と所要期間を事前に把握しておくことが重要です。
① サービス選定・比較(1日~1週間)
まずは自社の業種・取引規模・回収手段に合った収納代行サービスを選定します。手数料や提供機能、導入実績、サポート体制などを比較検討し、最適な業者を絞り込みましょう。
② 問い合わせ・ヒアリング(1~3日)
選定した業者に問い合わせを行い、自社の業務フローや希望条件を伝えます。ヒアリングにより最適なプランや必要書類が明確になります。
③ 見積もり取得・契約手続き(1週間程度)
業者からの見積もりや契約内容を確認し、問題がなければ契約に進みます。この段階で初期費用や手数料体系なども確定します。
④ システム連携・帳票確認(1~2週間)
請求データのフォーマット調整や、コンビニ払い用紙などの帳票設計を行います。業者のシステムと自社の会計・販売管理ツールとの連携も必要に応じて実施されます
⑤ テスト運用・本番開始(1週間)
初回のデータ送信や支払テストを実施した上で、本番運用に移行します。全体で1カ月程度が導入の目安となります。
特に初回は社内調整や帳票デザインの確認なども発生しやすいため、余裕を持った導入計画を立てましょう。
よくある質問(FAQ)
収納代行サービスを検討する中で、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
収納代行と決済代行はどう違う?
収納代行サービスは、サービスや商品の代金を企業に代わって顧客から回収し、その代金をまとめて企業に送金するサービスです。主に、コンビニ払いに対応しており、特にBtoC(消費者向け)の取引に多く使われます。これにより、企業は回収業務を効率化することができます。
一方、決済代行サービスは、コンビニ払いだけでなく、クレジットカードや電子マネー、バーコード決済など複数の決済手段に対応しています。特にECサイトなどでは、お客様が希望する決済方法がない場合、サイトを離脱してしまう要因になるため、複数の決済手段をまとめて導入できる決済代行サービスが向いています。
関連記事:収納代行とは?決済代行との違いやメリット・デメリットを解説
領収書の発行者は収納代行会社?自社?
基本的に領収書の発行は企業(=自社)の責任です。収納代行会社はあくまで「集金を代行する存在」であり、税法上の売上主体ではありません。そのため、顧客から「領収書がほしい」と要望があった場合は、自社で対応する必要があります。
ただし、代行会社によっては「領収書のテンプレート提供」や「発行補助サービス」がオプションで用意されていることもあるため、契約時に確認しておきましょう。
顧客からの問い合わせはどこが対応してくれるのか?
通常、収納代行サービスを導入した場合でも、顧客対応の窓口は基本的に自社(サービス提供者)側が担うケースが一般的です。顧客が疑問を感じるのは請求内容や支払い方法、領収書などの点であるため、サービスや商品内容に関する問い合わせには自社が責任を持って対応することになります。
ただし、決済エラーや支払いステータスの確認、再発行依頼など、決済に直接関係する技術的な問い合わせについては、収納代行会社がサポートしてくれることもあります。そのため、導入前に「どこまでを自社で対応し、どこから先は収納代行会社に委ねられるのか」というサポート範囲の明確化が重要です。
まとめ
収納代行サービスは、請求業務の効率化や未回収リスクの軽減に有効な手段ですが、その導入には手数料や契約条件、運用面での注意点も伴います。単に「料金が安い」という理由だけで選ぶのではなく、サポート体制や業界での実績、自社の業務フローや顧客との関係性に適したサービスかを総合的に判断することが重要です。
また、売上規模や業種によって最適なサービスも異なるため、自社にとっての導入タイミングや効果を見極めながら検討しましょう。この記事を参考に、安心して収納代行サービスを導入できる一歩を踏み出していただければ幸いです。