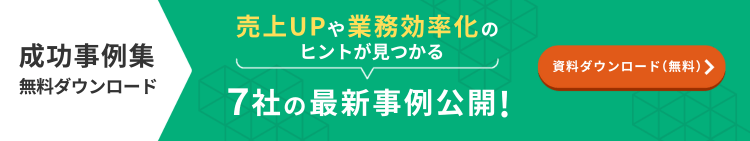【2025年3月末まで】3Dセキュア2.0の導入義務化!ECサイトで必要な対応と注意点
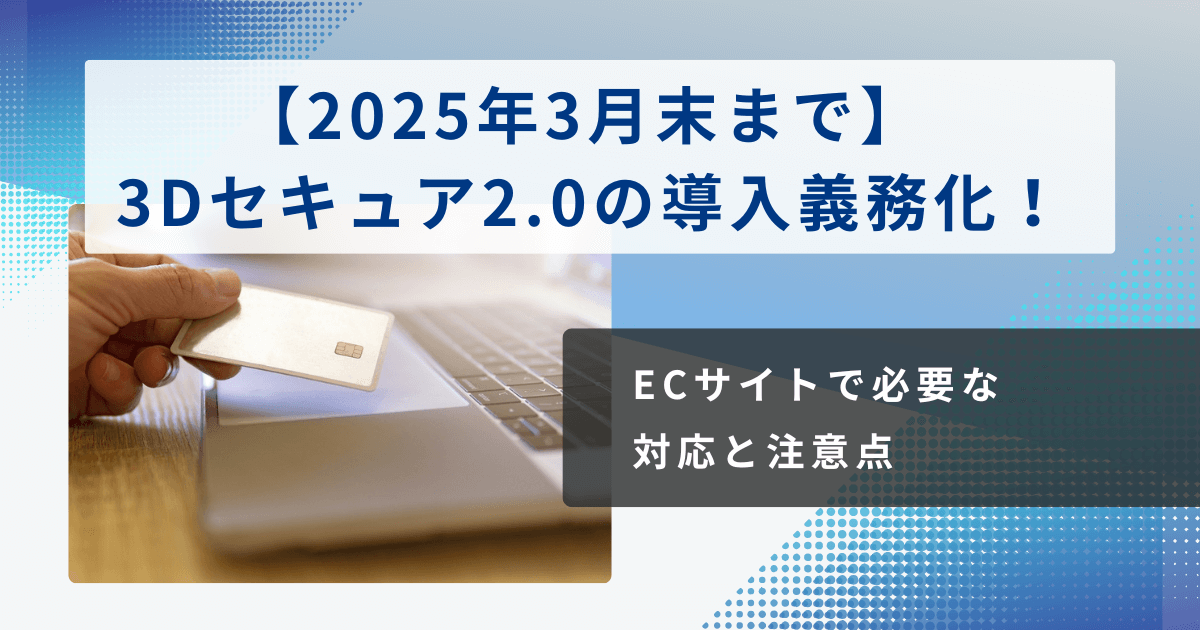
近年、ECサイトを狙ったクレジットカードの不正利用やオンライン詐欺が増加しており、消費者のセキュリティ意識も高まっています。こうした背景を受け、クレジットカードブランド各社は3Dセキュア2.0の導入を推進し、2025年3月末までの対応義務化を決定しました。
「3Dセキュア2.0ってそもそも何?」「自社のECサイトはどのような対応が必要なのか?」と不安に感じる事業者の方も多いでしょう。本記事では、3Dセキュア2.0の基本的な仕組みから、対応義務化の背景、対応方法や注意点まで、徹底的に解説します。
目次
3Dセキュア2.0とは?
3Dセキュア2.0は、オンライン決済におけるセキュリティ強化のために導入された認証プロトコルです。従来の3Dセキュア(1.0)を進化させ、不正利用の防止とユーザーの利便性を両立させることを目的としています。まずは、3Dセキュアの基本的な仕組みと、3Dセキュア2.0の特徴について詳しく見ていきましょう。
関連記事:3Dセキュア2.0とは?メリット・デメリットと対応方法を徹底解説
そもそも3Dセキュアとは
3Dセキュア(3D Secure)は、オンライン決済時の不正利用防止を目的とした本人認証技術です。オンラインでのクレジットカード決済の際に、本人確認を行うことでセキュリティを強化し、カードの不正利用やチャージバック被害を防ぐ仕組みとして導入されました。
「3Dセキュア」という名称の「3D」は、三者間(Three Domains)の認証を意味しています。具体的には以下の3つのドメインが含まれます。
- 発行者ドメイン(Issuer Domain):クレジットカードの発行会社(カード会社)
- 事業者ドメイン(Acquirer Domain):ECサイトの運営者や加盟店
- インフラドメイン(Interoperability Domain):認証をサポートするネットワーク(VISA、Mastercardなど)
これらの三者が連携して本人確認を行うため「3Dセキュア」と呼ばれています。
従来の3Dセキュア(3Dセキュア1.0)の仕組み
従来の3Dセキュア(1.0)では、オンライン決済時にクレジットカードのパスワードやPINコードを入力する形式が一般的でした。この方式には以下のような課題がありました。
- UXの悪化:認証画面が別ウィンドウで表示され、消費者が混乱することが多かった。
- 固定パスワードのリスク:パスワードの使い回しや漏えいによる不正利用リスクが高い。
- 対応端末の制限:モバイル端末では動作が不安定で、認証が完了しないケースがあった。
これらの課題により、消費者が認証を拒否したり、購入を途中で断念するケースも見られました。
3Dセキュア2.0の特徴と違い
3Dセキュア2.0は、EMVCo(国際的なカード決済標準化団体)が策定した次世代の本人認証サービスです。1.0の課題を解決しながら、よりスムーズで安全な決済体験を提供することを目的としています。
3Dセキュア2.0の主な特徴は以下の通りです。
- フリクションレス認証:リスクベース認証を採用し、安全性が確認できる取引は追加認証なしで決済可能。
- 多様な認証方法:パスワード入力の代わりに、生体認証(指紋認証、顔認証)、ワンタイムパスワード(OTP)、SMS認証などを活用可能。
- デバイス対応の強化:PCだけでなく、スマートフォンやタブレットなどのモバイル環境でも快適に利用可能。
- UXの向上:認証画面の遷移を減らし、シームレスな決済フローを実現。
3Dセキュア2.0義務化の背景
3Dセキュア2.0の対応は、すべてのEC事業者で2025年3月末までに義務化されています。これは国際的な決済カードブランド(VISA、Mastercard、JCB、American Expressなど)が要求しているものであり、オンライン決済を提供するすべてのECサイトが対象です。
期限以降、3Dセキュア2.0に対応していない場合、クレジットカード決済の拒否や取引自体が行えなくなる可能性があります。そのため、早期の対応が求められています。
3Dセキュア2.0が義務化される背景には、下記の点が挙げられます。
- オンライン詐欺の増加
EC市場の拡大に伴い、クレジットカード情報の不正利用が急増しています。特に、不正なスキミングやフィッシング詐欺によるカード情報漏洩が大きな課題です。
- 国際的なセキュリティ基準の厳格化
PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)などの国際基準に基づき、取引の安全性を高めるために3Dセキュア2.0の導入が求められています。
- 消費者のセキュリティ意識の向上
個人情報の保護やクレジットカード不正利用への不安が高まる中、セキュリティ強化の要請が高まっています。3Dセキュア2.0は消費者保護の観点でも有効です。
3Dセキュア2.0対応でECサイトがすべきこと
3Dセキュア2.0の義務化に伴い、ECサイトの運営者はシステムの改修や消費者への対応を適切に行う必要があります。未対応のままでは、決済手続きがスムーズに行えなくなり、取引機会の損失やセキュリティリスクの増加につながる恐れがあります。
ここでは、ECサイトが3Dセキュア2.0対応のために行うべき具体的な取り組みについて解説します。
システム改修の検討
3Dセキュア2.0に対応するためには、ECサイトのシステム改修が必要です。特に以下の点を確認し、必要な対応を行いましょう。
- 決済システムの対応状況の確認
利用中の決済代行業者が3Dセキュア2.0に対応しているか確認します。未対応の場合は、別の業者への切り替えを検討する必要があります。また対応している場合でも、新たに契約が必要だったり、システムのアップデートや改修が発生したりすることもあるので、早めに確認を進めといいでしょう。
- システムの開発・改修
3Dセキュア2.0ではリスクベース認証を採用しているため、取引履歴や顧客データを活用したリスク評価の実装が求められます。またスマートフォン、タブレット、PCなど、さまざまなデバイスからのアクセスに対応できる設計や、アプリ内ブラウザでも認証が機能する設計などが注意です。
個人情報管理の対策
3Dセキュア2.0の導入により、クレジットカード情報の取り扱いだけでなく、その他の個人情報の適切な管理もより重要になります。3Dセキュア2.0を導入するEC事業者が管理すべき主な個人情報には、以下のものがあります。
- 本人認証に関わる情報
氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日など - 購入履歴・取引履歴
過去の購入履歴、決済方法、配送情報など - デバイス・アクセス情報
IPアドレス、ブラウザ情報・デバイス情報、ログイン履歴など
これらを管理するうえで下記の点に注意をし、対策を行う必要があります。
- ユーザーの同意とプライバシーポリシーの明確化
ユーザーに対して、どのような個人情報を収集し、どのように利用するのかを明確に説明するプライバシーポリシーを策定し、同意を得ることが必要です。ユーザーが情報削除を希望した場合の対応ルールも整備する必要があります。
- セキュリティ対策の強化
社内でのアクセス権限を適切に設定し、業務上必要な従業員のみにアクセスを許可するといった管理体制や、情報の暗号化、ファイアウォールやWAF(Webアプリケーションファイアウォール)の導入による不正アクセス対策など、厳重なデータ管理体制の構築が求められます。
利用者への周知・サポート
3Dセキュア2.0の導入後は、利用者への適切な周知とサポートが重要です。認証プロセスが変わることで、購入時に混乱が生じないように配慮しましょう。
- 認証フローのわかりやすい説明
FAQページやブログ記事などで、3Dセキュア2.0の仕組みと安全性について詳しく解説するページを設置するといいでしょう。また、購入時に3Dセキュア2.0の認証画面が表示された際、認証方法の説明や問い合わせ先の案内をわかりやすく表示するポップアップなどがあると親切です。
- 問い合わせ対応の強化
認証エラーが発生した際に、チャットボットやFAQページを活用して迅速な対応ができるよう、カスタマーサポートの充実させることが重要です。認証失敗時には、再試行の方法や他の決済手段を提案するなど、エラー時の対応フローも整備することで購入体験への影響も最小限にできるでしょう。
法人のEC利用に対する影響
個人だけでなく法人も利用するECサイトでも、クレジットカード決済がメインとなっていることは少なくありません。法人向けのクレジットカード(コーポレートカード、ビジネスカード)も、3Dセキュア2.0に対応する必要が出てきていますが、法人カードの決済プロセスは個人向けカードと異なるため注意が必要です。
多くの法人では、クレジットカード決済をする際、経理部門にクレジットカードを借りてカード情報を入力したり、経理が直接カード情報を入力したりするのが一般的でしょう。そこで3Dセキュア2.0の認証プロセスが発生し、例えばOTP(ワンタイムパスワード)による承認が必要になると、OTPが経理担当者もしくは決済責任者のスマートフォンに送信される仕組みの場合、実際に購入手続きを行う社員との間で認証情報を共有する手間が発生します。
また一枚の法人カードを複数の担当者が共有して使用することもあるため、その場合3Dセキュア2.0の本人認証がスムーズに行えないケースが発生する可能性もあります。
企業の購買担当者が商品を選定し、上司の承認を経て決済を行うといったプロセスを踏む場合、3Dセキュア2.0の本人認証が追加されることで、承認フローを変更する必要も出てくるでしょう。
クレカ決済のカゴ落ち対策として請求書払いを導入すべき
これらの影響から、法人ユーザーが「手続きが面倒」と感じ、カード決済の利用を避ける可能性があります。法人向けにもクレジットカード決済しか用意していない場合、カゴ落ちが増加することは避けられません。その対策として、請求書払いを導入することがおすすめです。
ECサイトに請求書払いをカンタンに導入できるPaid
「Paid(ペイド)」は、請求業務の代行と未入金時の保証がセットになった企業間決済サービスです。ECサイトにも簡単に導入でき、判断が難しい与信審査も、小口取引が増えることで負担になる請求業務もすべてPaidが代行します。
未入金リスクだけでなく、不正利用を検知する仕組みもあるため、不正利用リスクも低減できます。
関連記事:決済方法の選択肢の多さが売上に大きく影響~株式会社キャンドゥ様の事例
まとめ
3Dセキュア2.0の義務化は、オンライン決済のセキュリティ強化と消費者保護の観点から非常に重要な取り組みです。システム改修や消費者サポートなどの対応はコストを伴うものの、適切に導入すれば不正利用のリスク軽減と信頼性の向上、さらにはコンバージョン率の改善といったメリットがあります。
2025年3月末の期限までに対応を完了し、消費者にとって安全で使いやすいオンライン決済環境を提供しましょう。