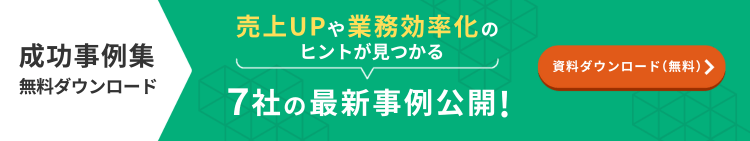売掛金とは?混合しやすい勘定科目や具体的な仕訳例を解説

売掛金とは、後払いによる取引で代金の支払いを受ける権利を言います。売掛金を理解するには、BtoBにおける信用取引(掛け取引)ついて知っておくことが重要です。信用取引によって取引機会の拡大につながる一方で、売掛金の未回収リスクを負うことになります。
本記事では売掛金とは何かを仕訳例についても触れたうえで、売掛金管理のポイントについて解説します。
目次
売掛金とは
売掛金とは、企業が取引先に商品やサービスを後払いによる取引で販売した際に、まだ受け取っていない金額のことです。つまり「未収の売上金額」を指し、取引先から後日代金を受け取ることが約束された金額を計上する際の勘定科目でもあります。売掛金は、貸借対照表の資産として分類され、将来的に現金などの形で回収されることを期待して記録されます。
商品やサービスを後払いで購入した側にとっては、後払いで支払わなければならない代金は買掛金になります。
売掛金で知っておきたい2つのキーワード
売掛金について知っておきたいキーワードとして、「信用取引」と「債権」が挙げられます。信用取引は、BtoB取引はもちろん、飲食店のツケ払いも該当する取引手法です。売掛金はBtoB取引や飲食店で、商品やサービスの代金を後払いにすることによって発生します。
信用取引(掛け取引)とは
BtoBでは、商品やサービスの購入代金をその場で支払うことは限定的です。商品やサービスの販売などの取引を行うたびに、代金の支払いを受けていたのでは、取引回数が多いほど、手続きが煩雑になってしまうためです。
そこでBtoBでは、先に商品やサービスの提供を行った後、一定期間の代金をまとめて回収する取引方法をとるのが主流です。こうした取引方法は、将来相手が代金を支払わないリスクがあり、信用を与える(=与信)ことで成り立っていることから、信用取引(掛け取引)と呼ばれています。
関連記事:与信管理とは?与信承認から事後管理までの具体的な方法と重要性を解説
信用取引で発生する「債権」とは
債権とは、特定の人に対して特定の行為を請求する権利のことです。信用取引における売上債権とは、受け取っていない商品やサービスの代金を請求する権利になります。売掛債権には売掛金と受取手形があります。
未収入金・未収収益・買掛金との違い
売掛金と似た勘定科目に未収入金、未収収益、買掛金などがあります。これらは混同しやすいですが、それぞれ異なる勘定科目として理解しておきましょう。
未収入金との違い
売掛金が主たる営業品目の販売で発生する企業が受け取るべき金額なのに対し、未収入金はそれ以外の売上(例:固定資産の売却代金など)に対してまだ受け取っていない代金を指します。資産として計上される勘定科目です。
未収収益との違い
未収収益は、企業が通常の営業取引で一定の継続する契約によって生じた商品やサービスの対価として得られるべき収益が、まだ受け取れていない場合に使用する科目です。例えば、貸付金の利息や賃貸物件の賃料など、サービス提供や権利行使による対価が未収の場合に使われます。売掛金は主に商品の販売やサービス提供による売上収益に関連しますが、未収収益は権利や契約に基づく受取額に関連します。また、未収収益は発生主義に基づき、収益が発生した時点で計上される点が特徴です。
買掛金との違い
買掛金は、企業が商品やサービスを購入したものの、代金をまだ支払っていない場合に使用する科目です。これは売掛金の逆に当たります。売掛金は「債権」(受取側の権利)ですが、買掛金は「債務」(支払側の義務)です。
| 勘定科目 | 意味 |
|---|---|
| 売掛金 | 通常の営業取引で商品やサービスを提供して生じた代金のうち、将来代金を受け取る 権利があるもの |
| 未収入金 | 営業活動以外の取引による代金のうち、未回収のもの |
| 未収収益 | 通常の営業取引で一定の継続する契約によって生じた商品やサービスの代金のうち、 未回収のもの |
| 買掛金 | 通常の営業取引で商品やサービスの提供を受けて生じた代金のうち、将来代金を支払う 義務があるのもの |
売掛金処理の流れ
売掛金処理は通常、次の流れで行います。
1. 売上計上
2. 入金確認
3. 売掛金の入金消込
商品やサービスの提供を行ったタイミングで売上計上を行います。支払期日に入金確認を行った後、売掛金の入金消込を行うという流れです。
売上計上
売上計上は、商品やサービスの売上を帳簿に反映することです。売上計上は、商品やサービスの提供が完了したタイミングで行います。売上計上を行う基準には、商品を出荷した日とする出荷基準、取引先に引き渡した日とする引き渡し基準、取引先が検収を行った日とする検収基準などがあります。
入金確認
入金確認は、売掛金の支払期日などに取引先からの入金の有無を確認する作業です。入金日、振込名義、案件名、金額を確認して、請求内容との相違がないかチェックします。
複数の案件の取引がある取引先からの入金は、まとめて入金されるケースと案件ごとに入金されるケースがあり、どの案件に対する入金か、確認が必要です。請求金額と入金金額に違いがある場合には、納品書をチェックしたり、営業に値引きや返品の有無を確認したりするなど、原因を調査した後、取引先に問い合わせを入れます。また、支払期日を過ぎて入金がない場合には、営業担当者に督促をするように促します。
売掛金の入金消込
入金消込は売掛金の入金が確認できたタイミングで行う作業です。売掛金の入金消込とは、売掛金として計上した金額が入金されたことを帳簿に反映して、売掛金を消すことをいいます。
関連記事:入金消込とは?具体的な作業の流れやよくある課題、システム化のメリットを解説
【ケース別】売掛金の仕訳例
売掛金の代表的な仕訳例として以下のケースをまとめました。
- 売掛金の仕訳
- 売掛金の回収
- 売掛金が一部回収できた場合
- 返品処理を行う場合
- 値引きする場合
- 売掛金が回収不可能な場合
- 買掛金と相殺する場合
複式簿記では、勘定科目を記載する帳簿の左側が「借方」、右側が「貸方」で、取引の原因と結果を左右に分けて記帳します。また、借方と貸方の金額は必ず一致するようにします。
商品やサービスの提供を行った時に、その場で代金の支払いを受けない場合は、売掛金として計上し、入金時に入金消込を行います。売掛金の一部が入金された時も、基本的に記帳の方法は同じです。
返品処理をするには、売掛金入金の場合の逆仕訳を行います。売掛金は、相手の承諾があれば買掛金と相殺することも可能です。売掛金の回収が不可能となった場合は貸倒損失として計上しますが、税務上、一定の要件が設けられています。
売掛金の仕訳
商品やサービスの提供を行ったタイミングで、代金の支払いを受けない場合は売掛金として計上します。
例:信用取引で10万円(税込み)の商品を販売した。
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 100,000円 | 売上 | 100,000円 |
売掛金の回収
売掛金の入金があった時には入金消込を行います。
例:<銀行振込のケース>普通預金に売掛金20万円から振込手数料500円を引かれて入金された。売掛金から振込手数料が引かれた場合には、支払手数料の勘定科目で仕訳をします。
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 195,500円 | 売掛金 | 200,000円 |
| 支払手数料 | 500円 |
例:<クレジットカードのケース>クレジットカード払いで30万円の売上があり、クレジット会社より手数料5,000円を引いた額の入金があった。
1.クレジットカード売上の計上
売上を計上するする際に、クレジットカードでの支払いによる売掛金は、クレジットカード売掛金として、通常の現金払いによる売掛金とは区別しておきます。また、売上の計上時にクレジットカード会社の支払手数料の勘定科目を立てます。
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| クレジットカード売掛金 | 295,000円 | 売上 | 300,000円 |
| 支払手数料 | 5,000円 |
2.普通預金にクレジットカード会社からクレジットカード売掛金29万5,000円の入金があった
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 295,000円 | クレジットカード売掛金 | 295,000円 |
銀行振込の場合と同様に、売上時にはクレジットカード売掛金は売上の額として、入金があった際に支払手数料の勘定科目を立てる記帳方法もあります。
売掛金が一部回収できた場合
売掛金の一部が入金された場合の仕訳は、売掛金の全額が入金された場合と同様です。借方金額も貸方金額も入金された額となるため、後から見た時にいつの売掛金の一部が入金となったのかわかりにくい点には注意が必要です。会計ソフトへの仕訳の入力の際には、いつの売掛金の一部なのか記載しておくようにしましょう。
また、誤って売掛金の全額の入金消込をしてしまわないように注意が必要です。
例:普通預金に売掛金30万円のうち、10万円の入金があった。
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 100,000円 | 売掛金 | 100,000円 |
返品処理を行う場合
商品代金の入金前に商品が返品された場合には、売掛金から差し引く処理をするため、売掛金が発生した際の逆仕訳をします。
例:商品4個(1万円分)の返品があった。
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 10,000円 | 売掛金 | 10,000円 |
値引きする場合
売掛金を値引きした場合には、入金があった際に売上値引きの勘定科目を立てます。
例:売掛金2万円に対して値引き500円があり、普通預金に1万9,500円の入金があった。
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 19,500円 | 売掛金 | 20,000円 |
| 売上値引き | 500円 |
返品処理と同様に、売掛金が発生した際の逆仕訳をする方法もあります。
買掛金と相殺する場合
商品やサービスを販売した取引先が仕入れ先でもある場合には、承諾を得たうえで売掛金と買掛金を相殺することができます。売掛金のうち買掛金と相殺した額で計上します。
例:取引先の承諾を得て、売掛金30万円のうち20万円を買掛金20万円と相殺した。
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 200,000円 | 売掛金 | 200,000円 |
売掛金が回収不可能な場合
売掛金の回収が不可能で貸し倒れとなった場合は、貸倒損失として計上します。ただし、貸倒損失の計上が認められるには、税務上一定の要件がある点に注意が必要です。貸倒損失の計上は、法的な整理手続きなどで金銭債権が消滅したケースと金銭債権の全額の回収が不可能となったケース、一定期間の取引の停止後に支払いがないケースで認められています。また、貸倒損失は、売掛金の回収が不可能になったことが明らかになった事業年度で計上します。
例:貸倒引当金の設定はなく、売掛金30万円が貸倒れた。
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒損失 | 300,000円 | 売掛金 | 300,000円 |
消費税の取り扱いについて
売掛金の仕訳をする際には、消費税の扱いについても理解しておくことも必要です。まず、消費税の取り扱い方法として「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2種類があります。
「税込経理方式」と「税抜経理方式」
税込経理方式は、取引金額を消費税を含む「税込金額」で処理する方法です。消費税がそのまま売上や費用として記録されます。一方の税抜経理方式は、取引金額から消費税を分離して「税抜金額」で処理する方法です。取引ごとに税抜金額と消費税額を計算する必要があるため、経理業務がやや複雑になりますが、売上や費用に消費税の影響が出ないため、取引の実態をより正確に把握できます。
課税事業者の場合、税抜経理方式を採用することが一般的で推奨されます。ただし、場合によっては税込経理方式を選ぶことも可能です。免税事業者の場合、消費税の納税義務がないため、税込経理方式が一般的です。
税抜経理方式で売掛金の仕訳をする方法
上記で解説した売掛金の仕訳方法は、税込経理方式で処理する方法です。税抜経理方式の場合は、消費税10,000円を「仮受消費税」として別に計上し、売上には税抜金額のみを計上します。
例:信用取引で10万円(税率10%)の商品を販売した。
| 借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 |
| 売掛金 | 110,000円 | 売上 | 100,000円 |
| 仮受消費税等 | 10,000円 |
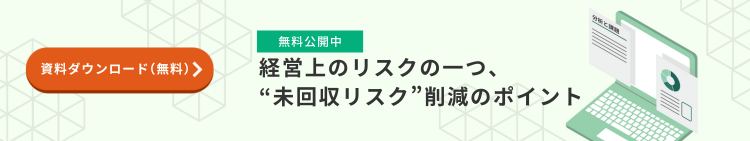
売掛金管理のポイント
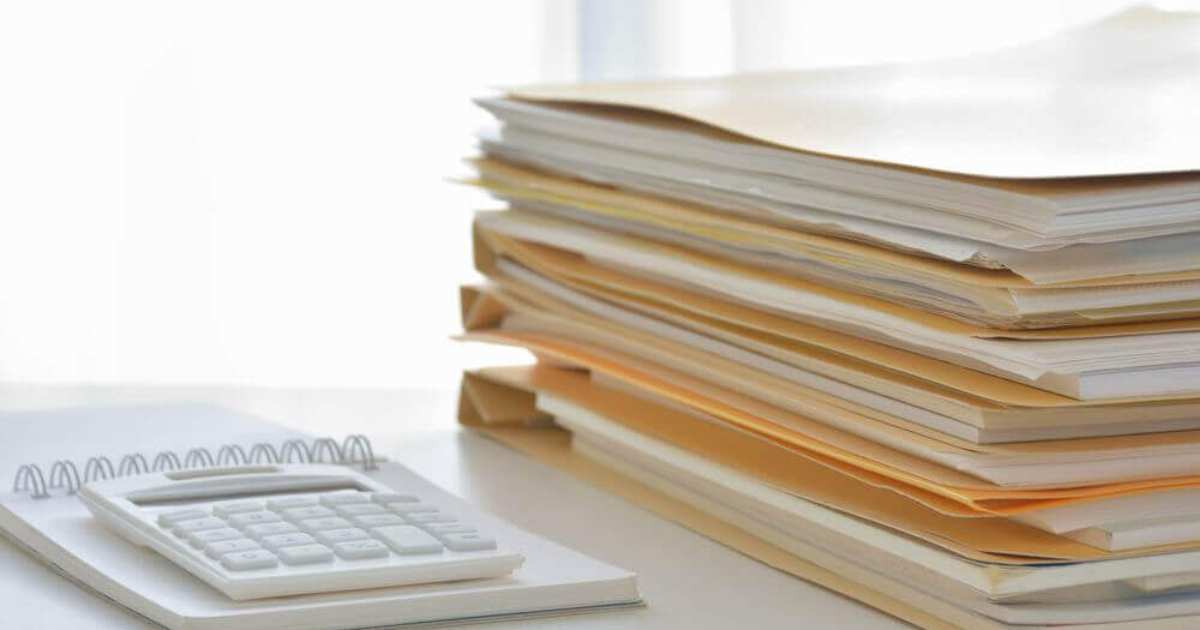
売掛金には未回収リスクがあり、長期間支払いが滞ることや倒産などによって支払いが不能になる可能性もあります。そのため、売掛金は適切に管理をしたり、未回収リスクが発生しない体制を構築したりすることが大切です。
売掛金管理のポイントなるのは、次に挙げる点です。
- 黒字倒産のリスクを軽減する
- 会計ソフトを活用する
- 定期的に売掛金を管理する
売上が上がっていても、売掛金の回収が滞ってしまうと、キャッシュフローが悪化して借入が必要となり、黒字倒産となるリスクがあります。また売掛金は企業の重要な資産であり、適切に管理することが重要です。
関連記事:掛売りの意味とは?メリット・デメリットを事例から紹介
黒字倒産のリスクを軽減する
信用取引では売上が増加すると、売掛金も増加します。売掛金が支払期日までに入金されていれば問題ありませんが、支払い期日までに入金がない状態であっても、買掛金や税金などの支払いをしなければ、ならなくなります。他方、税金は売上が増えれば増加します。
そのため、売掛金の回収が遅れるとキャッシュフローが悪化して、買掛金や税金の支払いが滞るようになってしまいます。そうした状態を解消しようと金融機関から借入を行うと、利息の支払いが発生することによって、ますます経営状態が悪化していくリスクがあるのです。すると、帳簿上は黒字であるにもかかわらず、手元に現金がないことから、最悪の場合、いわゆる黒字倒産を招くことになりかねません。
黒字倒産を防ぐには、信用取引のリスク軽減のための対策を講じることが必要です。
会計ソフトを活用する
ほとんどの会計ソフトには、売掛金を自動で仕訳する機能があります。取引が発生すると、自動的に売掛金を記録し、必要な勘定科目を割り当ててくれます。これにより、手動での仕訳入力作業を減らし、正確な会計処理が行えるようになります。 また入金消込機能も搭載されていることが多く、これを活用することで、売掛金と実際の入金を迅速かつ正確に照合することができます。入金が確認されると、会計ソフトは自動的に売掛金を減額し、入金額を記録します。手動での消込作業を削減することで、業務の効率化にもつながります。
定期的に売掛金を管理する
売掛金の管理は一度きりの作業ではなく、定期的に行う必要があります。特に月次や四半期ごとに売掛金の残高を確認し、未収金の状態や回収状況を把握しておくことが重要です。
定期的な管理を行うことで、以下のようなメリットがあります。
- 回収遅延のリスクを早期に発見し、対応策を講じることができる
- 不正な取引や記録ミスを未然に防ぐ
- 収益の流れをスムーズに保つことができ、キャッシュフローの改善にもつながる
売掛金が長期間未回収のまま放置されることのないよう、定期的にチェックを行いましょう。
関連記事:売掛金残高を管理するポイント~残高が合わない時の対処方法も紹介
経理業務を効率化するなら「Paid(ペイド)」
売掛金は取引先ごとに管理する必要があるため、取引先が増えれば増えるほど管理コストが増え、経理業務を圧迫してしまいます。
「Paid(ペイド)」は、請求業務の代行と未払い時の保証がセットになった企業間決済サービスです。取引先への請求・回収をPaidが行い、全ての取引先への請求金額を一本化して貴社にお支払いするため、取引先ごとの未払金の管理も不要になります。
経理業務を効率化することができれば、空いた時間を財務分析や外部とのコミュニケーションなど、事業を拡大するための業務に使うことができるようになります。
関連記事:3人は必要な経理業務が1人で対応可能!決算スケジュールも短縮できています~株式会社Saleshub
まとめ
BtoBでは信用取引がほとんどですが、売掛金管理を適正に行うことが重要です。多くの売上が上がっていても、売掛金の回収が滞ってしまうと、キャッシュフローが悪化して倒産してしまうことが起こり得ます。 しっかりとした管理体制を整えることで、売掛金の仕訳に関するリスクを最小限に抑え、健全な経営を支えることができるでしょう。